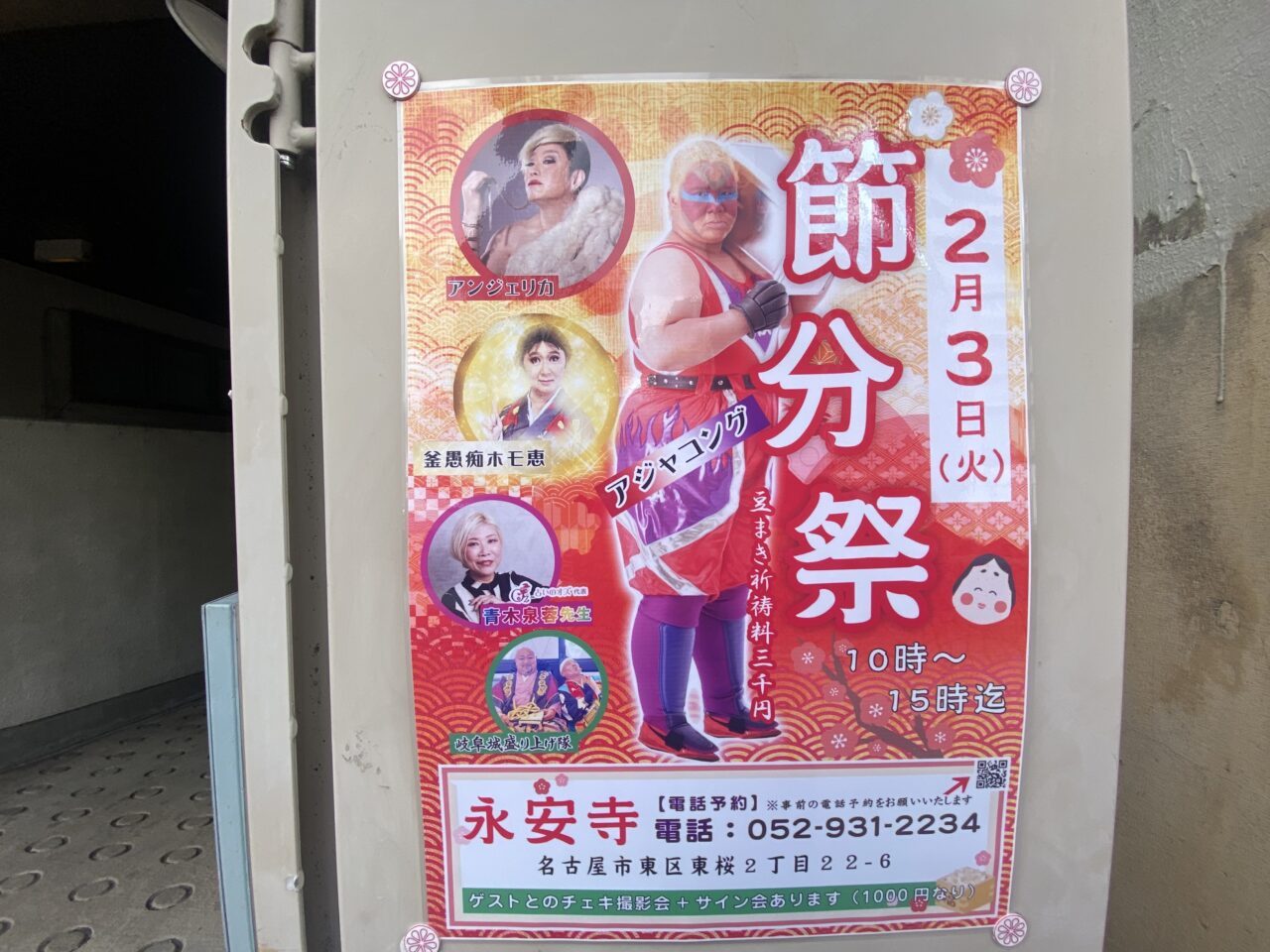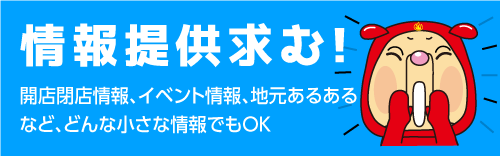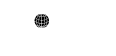【名古屋市東区】現役の先生がクラフトビール会社を起業!?教育とビール造りをつなぐ「Dragon Brewing.」
 名古屋市東区発!これまでにない斬新なクラフトビール会社が誕生しました!
名古屋市東区発!これまでにない斬新なクラフトビール会社が誕生しました!
その名も 「Dragon Brewing.(ドラゴンブルーイング)」。実はこの会社を立ち上げたのは、なんと東区にある私立中高一貫校の現役教員たち。授業を行う一方で、自らクラフトビールの醸造にも取り組む“教師起業家”たちなのです。
「生徒たちに教員が挑戦する姿を見せたい」そんな想いから、教育と起業をつなげる挑戦が始まりました。
先生たちがビール会社を立ち上げた理由

朝の仕込みの準備をする杉本さん
「Dragon Brewing.」のメンバーは、理科・英語・国語の教員5名に社会人2名。進学校ということもあり“いい大学”に入るための“勉強”だけにフォーカスしてしまいがちな生徒たちに、学生のうちに「起業」という正解のないチャレンジにして欲しいという想いから、2023年、学内で「ビジネス愛好会」を立ち上げたのだそうです。
愛好会の活動を通して起業について学ぶなか「教師自身が起業してそのプロセスを生徒たちに見せよう」と決意。最初は教育関連の起業を考えていたそうですが、インキュベーション施設での相談で「教育は難しい」とあっさりと却下されてしまったそうです。
「どうしようか……」メンバーとの雑談中に「ビールを作れたら楽しいな」という話になり、クラフトビールの会社を立ち上げることになったのだとか。
若者の“ビール離れ”が進む昨今、敢えてビールに挑戦する理由とは!?
Dragon Brewingのフルーツビールとは

ミックスベリーエール※画像提供:株式会社Dragon Brewing.様
代表を務める杉本有優さんは、学校では生物科の非常勤講師。もともとすごくビールが好きという訳ではなかったそうですが、農学系の学部出身こともあり、発酵についての知識があることや、ビールの原料の多様性に着目したのだそうです。
―――お酒の中でも敢えてビールを選んだのは何故でしょうか?
杉本さん:日本のビール業界はまだ大手メーカーが主流で、苦みが強くていわゆる“のどごし系”。苦手な人にとっては「おなかにたまる」「炭酸が強い」「麦感が強い」といった印象があります。
若者がビールから離れて、レモンサワーやジンなど他の選択肢に移行している傾向があります。私自身も、実はビールがあまり選択肢に入ってこないんです。
ただ、色々な原料が使えるという意味でビールはすごい。アメリカではハロウィンシーズンにかぼちゃのビール「パンプキンエール」を作る文化がありますし、イギリスでは生姜を使った発酵性飲料「ジンジャービア」があります。
そういった文化を考えると、いろいろな素材を試してもOKなんです。他にも、柑橘系の香りがする木の枝を使ったりと、本当にいろんな素材があるんですよ。これがウイスキーやワインだと、こんなに多様な素材を入れられません。ビールはそういう意味で自由度が高いんです。
―――どこかでビール造りを修業されたのでしょうか?
杉本さん:日本の法律上、家庭でビールを作ることができないんです。酒税法で免許を持っていないと勝手に作ると法律に反してしまいます。そのため試作ができないんですよね。研修に行って作らせてもらうか、海外に行って教えてもらうしかありません。
たまたまヨーロッパに行く機会があって、その際に、ベルギーとドイツのビールの様子を見てきたんです。ベルギーではカシスやラズベリー、チェリー(日本のさくらんぼより少し酸っぱい)などのフルーツビールがたくさんあって、スーパーの一角がフルーツビールコーナーになっているんです。日本では考えられないことですよね。

※画像提供:株式会社Dragon Brewing.様
杉本さん:ベルギーのビール工場へ飛び込みで行って、造る過程も見せてもらいました。日本でビール工場を作るんだという話をすると、結構いろいろ教えてくれるんです。材料が全然違うから日本で同じものは作れないけれど、途中の製造過程や商品になっていないものも見せてくれたり、試飲させてくれたりと日本にはない新しい知見を得ることができました。

ビールに使用する麦と大麦
クラフトビールの醸造には「酒類醸造免許」が必要不可欠。醸造免許取得のために「醸造研修」が必要となるため、お手本となる小規模ブルワリーを探したという杉本さん。そこで島根県の「石見麦酒」さんと出会います。
醸造の一連の流れを1ヶ月間みっちり「石見式」で学び、その後ほぼ最短の4ヶ月で醸造免許を取得(取得に至るまで分厚い書類をチェックするやりとりが何度もあったのだとか!)。

石見式のボトル充填機
―――Dragon Brewing.のビールはフルーティーな味わいになりそうですね。
杉本さん:私たちが今仕込んでいるものには8種類のフルーツが入っています。ブドウ、カシス、ラズベリー、クランベリー、あまり有名ではないですがリンゴンベリーといったベリー類、ブルーベリーなど、ベリー系が多めです。8種類もの果物を入れるので後味には深みがありますが、前面に出てくるのはやはりフルーツの風味です。
今のビール業界の常識からすると、これだけ果物を入れるのはかなり挑戦的で、もしかするとネガティブな反応があるかもしれないほどです。でも、ビールが苦手な人には飲みやすいビールだと思います。また、フルーツだけでなく、生徒と一緒に育てた野菜もこれから使っていきます。生姜やかぼちゃなどですね。
―――販売予定のビールは何種類あるのですか?
宮地さん:初回は2種類のビールを作りました。一つは8種類の生フルーツを使ったベリー系のフルーツビールです。もう一つはザクロやリンゴ、バニラが入った商品です。バニラの風味が効いていて、女性が好みそうな酸味があります。どちらも苦くなく、ワインに近い味わいですが、炭酸はしっかりあり、後味に麦の深みもあります。普通の人が飲むと、一般的なビールとは思わないかもしれません。
周囲の反応は?

英語教師でプレゼン担当の宮地邦樹さん
―――教員の兼業願いは学校の歴史の中でも初めてのケースだったのでしょうか?
宮地さん:そうですね。しかも、雇用としての兼業願いしかフォーマットがなく、私たちは取締役なので雇われているわけではないため、そもそも適切なフォーマットがありませんでした。現役教員で起業している人は、時間的制約や公立高校の規則などの理由で、ほとんどいないと思います。
―――校長先生に最初に相談した時の反応はどうでしたか?
宮地さん:学校が公式に推している活動ではないので、「学校名を使って販売などはしないでください」と言われましたが、基本的には「好きにやってみてください」という感じでした。私たちの学校は比較的自由な校風で、教員がさまざまな活動をしています
―――保護者やOBの方々からの反応はいかがですか?
宮地さん:とても応援していただいています。それを如実に感じたのはクラウドファンディングですね。2025年の2月から3月にかけて行ったのですが、334人から550万円の支援をいただきました。ほとんどが保護者やOB、生徒たちからで、非常に励みになりました。
また、ロゴのデザインや醸造所の改築、流通なども保護者やOBなどの関係者だったりと、つながりの大切さを感じました。
―――生徒さんからの反応はどうですか?先生たちの起業活動についてどう思っているんでしょう?
杉本さん:私が担当しているクラスの生徒たちの反応しかわかりませんが、過去に教えていた生徒が校内ですれ違うと「先生、ビールどうですか?」と聞いてくることもあります。
経済系に興味を持った生徒が「先生のところ株式会社ですよね。上場しないんですか?上場したら株を買ってあげます」なんて言ってくれることもあります(笑)。いろんな意味で影響を与えられていると思います。
―――先生たちが会社を作って、しかもビールというのは珍しいですよね。生徒たちも早く成人して飲みたいでしょうね。
杉本さん:そうなんです、それも実は結構大事だと思っています。すでに卒業した生徒たちは「飲みたい」と言ってくれますし、現役の生徒たちがどう反応するか気になっています。
中には「先生たちとコラボしたいです」と言ってくれる生徒もいて、今後「僕も会社を作りました」「こんなのがあるんですけど、ビールにできませんか」といった形でつながり始めたら面白いなと思います。
クラフトビールづくりの現場へ
 Dragon Brewing.の醸造所を見学させて頂きました!
Dragon Brewing.の醸造所を見学させて頂きました!
元は永井写真館さんの旧社宅。さらにその前は三味線を芸妓さんに教える方が住んでいたという、筋金入りの古民家でもあります。生徒の保護者の方が経営している設計事務所が改築を手掛け、古民家の味わいが残る小さな醸造所が出来上がりました。 小規模ブリュワリーなので、機械はDIYで制作。メンバーには物理の先生・松﨑旭洋さんがいるので改造はお手のもの。
小規模ブリュワリーなので、機械はDIYで制作。メンバーには物理の先生・松﨑旭洋さんがいるので改造はお手のもの。 煮込んだビールを発酵させるための冷蔵庫も、上部分をDIYで増築したのだそうです。
煮込んだビールを発酵させるための冷蔵庫も、上部分をDIYで増築したのだそうです。
小規模ブリュワリーの良いところは、万が一機械が壊れても低コストで直せたり、買い替えたりできるところ。大手のビール工場のようにたくさんのビールは作れませんが、小規模だからこその新たなチャレンジや、柔軟な対応がしやすいという強味があります。

作業するスタッフの松永卓也さん
元台所を改造した場所で、2階で挽いた麦と大麦を寸胴で煮込んでいきます。ビールづくりで一番大事なのは温度管理。酵母の働きや香りが変わってくるので、数度の違いが仕上がりに影響するので、あまり目が離せません。 現在は、醸造をマスターした杉本さんが授業のない日に醸造の日に設定し、他のスタッフさんと共に作業。週5日フルタイムの先生たちは働いているので、ラベル貼りや発送作業などを担当することが多いそうです。
現在は、醸造をマスターした杉本さんが授業のない日に醸造の日に設定し、他のスタッフさんと共に作業。週5日フルタイムの先生たちは働いているので、ラベル貼りや発送作業などを担当することが多いそうです。

麦汁を混ぜる代表の杉本さん
温度計をこまめにチェックしながらも、自社のビールについて生き生きと説明してくれる姿が印象的でした。発酵の仕組みについても、さすが生物の先生であります。分かりやすく説明して頂き理解が深まりました♪
購入方法と今後の展開

※画像提供:株式会社Dragon Brewing.様
気になる販売方法ですが、ビールの販売は醸造所では行わず、ネットショップを中心に販売中です(※2025年9月26日時点、第1ロット分のビールは売り切れ)。ネットショップでは「ミックスベリーエール」(6本入り/6,500円)のほか、オリジナルグッズも販売しています。
ネット以外では卸売の株式会社秋田屋から、デパートや酒屋などにも少しずつ流通する予定です。小規模生産のため、なかなか手に入らないかもしれませんが、ネットショップやSNSを小まめにチェックしておきましょう。

NICK BUCKER
また、東区筒井3丁目にある「NICK BUCKER」さんで、「ミックスベリーエール」を飲むことができます!(※売り切れの場合もあります)。チーズと合わせると絶品だそうでうよ♪
さらに、地域との連携にも力を入れています。今後、地元企業や地元店舗とのコラボ展開、生産途中で出る残滓を活かす工夫をしたりと、持続可能なものづくりを模索。すでに走りだしている企画もあるそうです!「Dragon Brewing.」は、単なるビールメーカーにとどまらず、地域社会と一緒に歩む存在を目指しています。

左から宮地邦樹さん、杉本有優さん、松永卓也さん、松﨑旭洋さん
実は取材中に製造工程でちょっとしたトラブル発生も(無事リカバーできたそうです)。
「今はこういったトラブルばかりで、もうボロボロな状態です(笑)。思い通りにいかないことが多く、「また失敗した」と感じることもありますが、なんとか立て直して次へ進むよう頑張っています!」
杉本さんはさらにこう語ります。
「多分、ロットによって最初は結構味にばらつきがあると思うんです。最初から期待値を高く購入してもらって「美味しかった」と思っても、次回「前回と違う」というようなことは結構ありうる話だと思います。ちょっと酸っぱいとか、ちょっと渋いかなとか、そういう味の違いがあります。でもそれは私たちの試行錯誤の中で生まれているものだと思ってもらいたいです。また、生徒たちにもちゃんと「失敗していいんだよ」ということを伝えたいです。今は着実に失敗しながらも美味しいビールを作っています!」
名古屋市東区から生まれた、新しい形のブルワリー。Dragon Brewing.の挑戦は地域と教育の未来に新鮮な刺激を与えてくれそうです。
「Dragon Brewing.(ドラゴンブルーイング)」はこちら↓